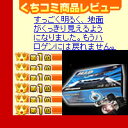- HIDとは |
- 選び方 |
- 取り付け&レビュー |
- 質問・疑問Q&A |
- メーカー別製品レビュー |
- クルマ専門ブログCLSD
H.I.Dとは(エイチアイディー)高輝度放電灯
What's H.I.D(High Intensity Discharged lamp)
HIDとは?
H.I.DとはHigh Intensity Discharged lampの略で、キセノンまたはディスチャージなどと呼ばれる明るいヘッドライトのことです。ハロゲンランプの数倍の明るさと消費電力の低さ、更にフィラメントがないため長寿命と言われ、注目を集める次世代ランプシステムです。
日本では1995年に認可されたのを受け、メーカーオプション・標準搭載の車種が増えてきました。社外品はあったものの10万を超える高値で、ファッション性のあるハロゲンバルブが高くても1万円くらいだったのと比べると、後付する人は少なかったでしょう。
しかし価格がだいぶ落ちてきたのと、製品ラインナップが豊富になったことで、ご使用される方が増えています。消費者が手の届きやすい場所に、多くのメーカーが投入し、激戦区となりました。
そこで見えてくる問題点と、後悔しないHID選びのポイントを、基本的なことから解説していきます。まずはHIDとは何か?
明るく省電力なヘッドライト
ヘッドライト、ヘッドランプと呼ばれる車の前方を照らすメインのライト・前照灯には従来から「ハロゲンランプ」が使われてきました。電球内部にハロゲンガスを封入するハロゲンは不活性ガスのみを封入する白熱電球よりも明るく、長寿命の電球である。
しかし内部のフィラメントに通電して発光を得るハロゲンは温度が高く、フィラメントを持たないHIDなどのヘッドランプに比べて寿命が短いなど、見劣りする部分が多いのは確かです。
唯一メリットと言えるのがコストだと思われてきましたが、昨今のHIDブームによって、それほど大きなアドバンテージにはなっていないというのが現状でしょう。それよりも日々価格が低下するHIDの製品に注目が集まるところです。
HIDは高輝度放電灯と略され、水銀灯や蛍光灯などと似たフィラメントを持たないアーク放電による光源のランプの総称である。高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプなどがある。
高輝度、高効率、長寿命で太陽光と色温度が近いなどの特徴があり、テレビや映画などの演出照明でも使われ、自動車や鉄道車両にも使われるようになった。
HIDに替わる技術として白色LEDが挙げられるが、省電力の代わりに明るさにおいては劣るため、一定の輝度を確保するには数個のLEDを用いなければならず、コスト的にもよくない。一部車両には採用されているので、今後の進歩によっては主流になる可能性はある。
実用化されたのは世界では1991年にドイツでBMW7シリーズが最初で、日本では1995年に許可され、三菱ふそうのスーパーグレートに設定された、乗用車では日産自動車のテラノである。
発光原理としてはキセノンガスなどを封入したバルブ内のアーク放電で発光する。放電灯の一種でキセノンなどの希ガスとヨウ化金属などの金属が封入され、点灯時のキセノンによる放電・発熱によって、金属を蒸発させ、混合蒸気中のアーク放電による発光を利用したメタルハライドランプまたはメタハラなどと呼ばれるものである。
点灯直後は希ガスのみの発光のため青白い光となる。本来の明るさや光の色へと安定するまで数秒から数十秒かかり、瞬間的な点灯はあまり得意ではない。そのためハイビームとロービームを切り替えるような場合は、可動する反射板などによって配光をかえる方法がとられる。
取り付けに関しては、電気を一度バラストなどの昇圧・安定させる機器に接続してそこから電気を供給してもらうので、多少配線が多くなりハロゲンからの交換になると、設置スペースなどを考える必要も出てきます。