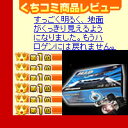- HIDとは |
- 選び方 |
- 取り付け&レビュー |
- 質問・疑問Q&A |
- メーカー別製品レビュー |
- クルマ専門ブログCLSD
買ったはいいけど、どうする?
取り付け時の注意点!
点灯テスト?
HIDキットが届き、明るいヘッドライトが手に入ると期待が膨らみますが、取り付けがすむまでは当然つかえません。取り付けの第一歩といえるのは、設置前の点灯テストです。とりあえずバラストとバルブやヘッドライトの配線をつないでみて、つくかどうかを確認することがはじめの作業となります。設置した後につかないでは、どうにもなりませんからね。
この点灯テストを行わなければ、保証の対象外とすることもあるそうで、重要な作業のひとつといえるのです。バルブの点灯テストはすみましたか。ちゃんと点灯していますか。つかない場合は、配線がちゃんとつながっているか、プラスやマイナスが間違ってないか、バッテリーがつながっているかなど基本的な通電を調べてから、製品の不良を疑いましょう。
〜ドキドキの初点灯〜
取り付けの際にやっておきたいことは、点灯テストです。ちゃんと設置する前に、とりあえずバルブがつくかどうかテストだけでもやっておきましょう。
意外と暗くない?
HIDバルブは、水銀灯と同じような仕組みをしており、点灯はじめは暗く感じるかもしれません。ハロゲンはつけて数秒で本来の明るさで光るのに対し、HIDは数十秒くらいは光の色や明るさが安定しません。取り付け直後に期待して点灯してみても、昼間など明るい時に確認すると本当に明るいのかと疑問に思うことがあるかもしれませんが、数秒程度では確認することはできません。
実際に日が落ちてから点灯してみて、暗く感じるでしょうか。ハロゲンの光と比較した場合、何倍くらい明るくなったでしょうか。逆にハロゲンの光が見にくいと感じることはないでしょうか。HIDの明るさはぜんぜん違います。試したことのない人、まだその明るさを体験したことのない人は、低価格化されコストパフォーマンスの高いシステムを、一目みてみてください。
〜スタートは苦手〜
HIDは光が安定するまでに少し時間が掛かります。ライトスイッチをオンにしてもすぐに明るさの最大レベルまではいきません。
青色は大丈夫?
HIDを選択するなかで迷ってしまうのが色温度のケルビンですが、真っ白といわれる6000Kか、少しおしゃれな青白い光にしたいと思う人もいるでしょう。6000Kをこえれば青くなっていくが、車検は微妙なところだ。青い光の特徴は、ハロゲンなどの黄色い光に比べてファッション性が高く、採用するクルマが少ないので希少であり、目立つこと間違いなしと思われるだろうが、車検には通らない可能性があり、雨の日は見づらいという致命的な部分がある。
青い光の透過性というのは低く、雨や霧などの天候が悪いときの明るさの変化は、顕著になります。ブレーキランプにも採用される赤や、フォグランプに多い黄色に比べると光が届かず、悪天候の視界確保は困難になります。別にそれでも青い光がほしいという人や、一般道路では走らないから別に関係ないというひとは、8000K以上の色温度も選択肢の一つになります。一応車検にはほぼ通らないと考えるべきです。
〜8000Kの蒼〜
車検に通るか通らないかは、8000Kあたりが分岐点となる。競技用車両でない限りは、6000Kあたりにしておくのが吉だ。
35Wと55Wを比較すると?
HIDを選ぶとき色温度をいくつにするか悩んだりしますが、その前に35Wか55Wかを検討してみてはいかがだろうか。ヘッドランプの基本的な能力は明るさですが、その能力を左右するワット数の違いは大きい。ほとんどの純正HIDに採用される35Wは、消費電力が少なく低燃費であると言われ、その割りに明るく実用的と言われている。確かにハロゲンランプと比べれば明るいし、消費電力も少ないのである。
しかし、ヘッドランプはまだまだ暗い。夜のドライブが昼間のドライブと比べて危険な部分があるとすれば、やっぱり見えにくいことだろう。歩行者、障害物、路面などライトが明るければもっと快適に走ることができる。HIDとハロゲンを比較した場合は、明らかに違いがあるが、それと同じくらいに35Wと55Wを比較したときは、明らかな違いがある。真の明るさを手に入れるには、やっぱり55WクラスのHIDだろう。
〜明らかな違い〜
ワット数の違いは直接明るさの違いに反映される。35Wと55Wでは、1.5倍以上の違いがあるので、その差は歴然。
脅威の明るさ!6,000ルーメンの実力?
HIDを選ぶポイントで、明るさは基本的な性能かつ重要な要素である。明るさの単位はlm(ルーメン)なのだが、カタログでは載っていない。ハロゲンと比べる場合は、その違いがよくわかる。全光束(ルーメン)が大きければ色温度(ケルビン)に関係なく明るく。逆に色温度が高すぎると、ルーメンが下がり明るさが低下してしまいます。ハロゲンランプは1,000lmから1,550lmくらい。HIDは、35Wで3,200lmから3,300lmくらいです。
メーカーによって多少の差はあるだろうが、構造的には同じヘッドライトなので、極端な明るさの違いはないだろう。明るさに重点を置くのならメーカーをこだわるよりもハイワッテージ(ワット数の大きな)HIDを選ぼう。55WのHIDは、脅威の6,000lmを実現する明るいヘッドランプです。ハロゲンの6倍、純正HIDの2倍の明るさを持つ55Wは、暗闇をまるで昼間のような感覚に変える明るさを見せ、夜でもはっきり路面や周辺を確認することができます。
安全面でも優れているHIDを装着すれば、ファッション性も向上し快適なドライブを楽しめる。純正HID装着車も55Wのハイワッテージバーナーに交換すれば、純正にはない明るさを手に入れることができる。
〜明るいヘッドライト〜
一般的なハロゲンランプは1,000lmから1,550lmくらい。対するHIDは、35Wで3,200lmから3,300lmくらいと3倍は明るい。そして脅威の6,000lmを実現する明るいヘッドランプが55WのHIDシステムだ。
紫外線が照射?
HIDはアーク放電によって光を発生させていますので、ハロゲンランプとは比較にならないほど紫外線が照射されます。紫外線は目には見えない不可視光線。太陽光は大気圏のオゾン層によって、そのほとんどを防いでいます。HIDバルブから発生される紫外線は、通常UVカット加工された石英ガラス管などで、外に漏れないようにしている。安価な粗悪品などはUVカット加工されてないものもあり、ヘッドライトレンズを劣化される恐れがあります。
ヘッドライトのカバーがアクリル樹脂などでは、紫外線の照射によって曇りなどがでて、反射鏡なども劣化が進むようだ。最悪の場合ヘッドライトレンズの交換ということにもなりかねない。安価なバルブで損害をうけないように・・HIDは、「透明度」「UVカット性能」「衝撃・振動耐久」などを考慮し、PHILIPS社製HIDバルブ専用石英ガラス管を採用したBRIGHT社製品をお勧めします。
〜ウルトラヴァイオレット〜
UVカットなど紫外線から守る化粧品や窓ガラスなどがあります。紫外線は波長によっていくつかに分類されますが、攻撃性が強く化学的な影響が大きいもので、その脅威から身を守るために対策がなされています。
雨の日のドライブ?
光は波長によって色が変わり、人が見えることのできる可視光線は、波長の長さによって赤から黄色に変わり青へと変化していく。赤より長い波長の見えない不可視光線は赤外線と呼ばれ、青より波長が短い不可視光線を紫外線と呼ぶ。赤い光は波長が長いため散乱しにくく、透過性が高いのが特徴です。逆に青い光は波長が短く透過性が低いため、雨の日など天候の悪い日は光が遠くまで届かず暗くなった印象を受けます。
HIDで代表的な6000Kなどの色温度は、比較的波長が短いため悪天候になるほど、光が透過しにくく暗くなる印象を受けます。実用性を考えると低い色温度の短い波長のランプを選ぶほうがいいかもしれません。お勧めは、メインのヘッドランプを6000Kなどの純白色で、サブのフォグランプなどに低めのイエローランプを入れることで、晴れた日も雨の日も霧の日も、安全なドライブを実現できる。
〜悪天候に弱い高い色温度〜
光は波長によって色が変わります。色温度ケルビンという単位で、色味を表現しているのですが、色温度の高い青みがかった光は、雨などの悪天候には弱いです。
色が安定しない?
オンオフが苦手なHIDですが、構造・動作原理に理由があります。ハロゲンのようにフィラメントを発熱・発光させる仕組みに比べ、いくつかのプロセスが組み合わさることで、発光の安定にわずかに時間が必要です。高電圧で放電が始まる時間は大したものではありませんが、発光管内の温度が上昇し、封入されたメタルハライドソルトが気化し、金属原子が励起することで発光すうという原理のため、温度や色の安定までに時間がかかってしまうようです。
アナログからデジタルバラストに変わったことで、多少の改善はみられたもののハロゲンやLEDのように瞬間的に安定するランプシステムに比べると遅く感じられるかもしれません。しかし瞬間的にオンオフを繰り返すような使い方はまれで、常時点灯していることが多いヘッドライトでは実用的には何の問題もありません。光の明るさと色の安定も1分程度で完了します。チラツキなどはまた別の問題です。
〜HIDって何〜
High Intensity Discharge lampの略(エイチ・アイ・ディー)は、高電圧をかけることで封入されたキセノンガスが電離しアーク放電をすることで、発光する新しいランプシステム。