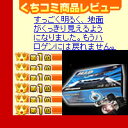- HIDとは |
- 選び方 |
- 取り付け&レビュー |
- 質問・疑問Q&A |
- メーカー別製品レビュー |
- クルマ専門ブログCLSD
用語解説・疑問質問
何に使うの?意味から教えて!
薄型デジタルバラストとは?
薄型デジタルバラストは、デジタルコントロールチップを搭載し、電圧や電流を正確に制御することで、安定した出力を得られます。また12Vや24Vに対応する汎用性の高さもあります。本体が薄型でコンパクトなことで、取り付け位置を自由にかつ容易に設置できるようになり、軽量ということも大きなメリットになります。また立ち上がりの時間が短くなる。
正確な電圧・電流制御はちらつきがなく一定の明るさを保ちます。安定した電圧電流が無理をさせないためバーナーやバラスト自体の寿命もよくなります。逆に安定しない点灯は寿命を縮める可能性もあります。さらにバラストに搭載される保護回路が、万が一のトラブルを最小限にします。色温度やワット数などバーナーの性能に目がいきがちだが、その性能を支えるバラストにもこだわりたい。
〜コントロールは正確なデジタル〜
HIDの心臓部とも言えるバラストは、バーナーの性能を最大限に発揮するために電圧や電流を制御しています。回路をデジタル方式にすることで、薄くてコンパクトなバラストになりました。
何ケルビンまでなら車検に通る?
HIDの車検については、保安基準を満たしていれば通り、保安基準に適合していなければ、通らないということだ。しかも特に何ケルビンと定められているわけでもなく、車検を行う人の判断によるところもある。実際に「白色または淡黄色」と言っても何ケルビンくらいかという基準はなく、6000Kを少し越えたあたりから、ハッキリとは言えないというような具合だ。通るかもしれないし、通らないかもしれない。
同じケルビン数でもメーカーによって、色が違うというので、青っぽかったり、紫っぽいと車検ではNGになる可能性はあります。フォグに限っていえば光度が1万cd以下と決まっているらしい。淡黄色にあたる2500KはH18.1.1以降の製作車では車検非対応になる。確実に通ると思われる範囲が4000K〜6000Kあたりで、HIDをとりあえずつけたいと思っているなら変な色温度は避けるべきだ。
〜車検対応HID〜
前照灯の保安基準では、灯光色は「白色」と規定され、(2005)平成17年12月31日以前に製作された車については、灯光色は「白色または淡黄色」と規定されている。
12V 6000K 55Wの実力?
HIDのバルブにはいくつも種類もあるが、35Wと55Wの違いは大きい。同じ出力なら4000Kから4300Kあたりが一番明るい色温度らしいが、6000Kは白く太陽光のような明るさを持つ。暗闇を照らす唯一の光はヘッドライトだから、できるだけ明るい方がドライバーは助かる。街灯の光も走るところ全てに備え付けてあるわけではないし、十分な光とはいえない。
スピードが出る車は急な動きが苦手だ。歩行者などの発見が遅れたために急ブレーキの必要が出てくるのでは、安全面で不安が残る。明るい光によって夜でも視界が広がることで、安全面の向上が期待できる。ハロゲンの光では夜はどうしても見えずらいが、HIDの光ならまるで昼間のように路面の状況が見えるようになる。遠くまでそして幅広く明るさが広がっているのが、よくわかる。
〜蒼白の閃光〜
6000Kのバルブの光は、点灯直後は青白く照らす薄明かりだが、安定してくると徐々に明るさを増し、純白の光が闇を切り裂く。55Wの高出力はハロゲンとは比べることもできないくらい明るい。
イエローバルブ、フォグランプ?
ヘッドライトとして使われるHIDの色温度は6000Kや8000Kなど、純白や蒼白の光が注目され、ファッション性や車検の合否に関心が向きがちだが、安全性・実用性を考えるともうひとつの選択肢がある。黄色い光を放つイエローバルブは、雨や霧などの悪天候時でも光の拡散が少なく、しっかりと光が届くのである。波長が短い青色の光は、透過性が低いこともあり悪天候ではみえずらいと評判だ。
もうひとつの選択肢イエローバルブは、実際の見やすさ明るさの面で、ほかのバルブよりも優れている。雨の日は夜のドライブとは違い、明るいだけではだめで透過性が高い光である必要がある。ヘッドライトをHID化するだけではもの足りない場合は、フォグにイエローバルブを入れるもの一つの案だ。だが明るすぎるHIDは、フォグランプに使用すると保安基準に適合しない場合もある。
〜全天候型ヘッドランプ〜
ヘッドライトは暗くなった夜に使うのが一般的な考え方だが、雨や霧など天候が悪いときにも活用できる光のお守りだ。視界を確保するだけでなく、自分の存在を示す道具にもなる。